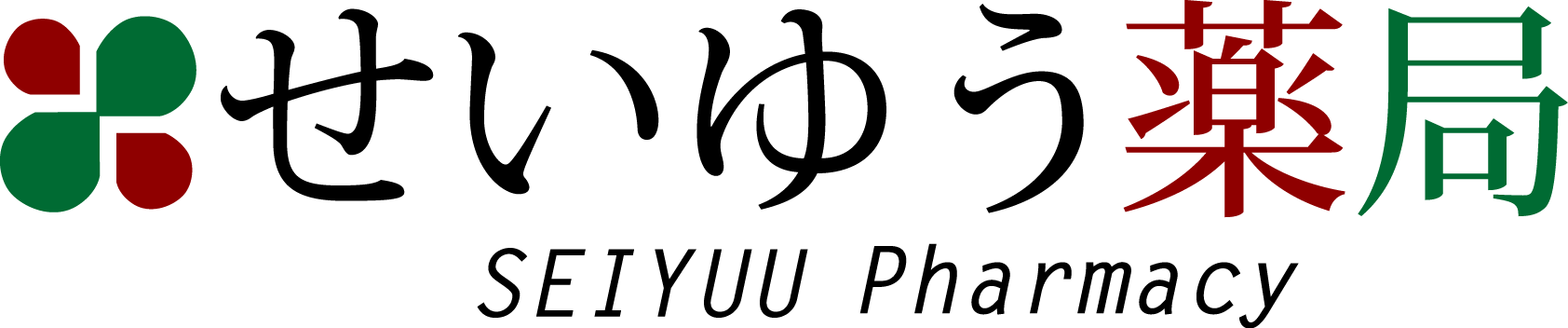こんにちは。
自律神経失調症/パニック障害専門のせいゆう薬局です。
漢方薬専門店でもあります。漢方薬だけでの治療を行っています。
(サプリメントや健康食品の販売は行っておりません。)
今回のひとりごとは
風邪薬の利用法について(西洋薬編)
です。
当店での漢方治療中のお客様から
「漢方薬と風邪薬の併用は可能ですか?」
と質問されることも多く、返答と併せてお伝えしていることがあるので
今回は風邪薬(西洋薬)の位置付けや利用法、有用性についてもお話していきます。
長くなりそうなので、風邪薬(漢方薬編)についてはまた別でお話していきたいと思います。
それではよろしくお願いします。
風邪薬は治療薬ではありません!
まずは西洋医学の風邪薬について重要な点をお話していきます。
風邪薬は治療薬ではありません!
大事なことなので見出しと同じことをもう一度書きました。
風邪を治療する薬があるとすれば、風邪ウイルスを死滅・抑制させることの出来る薬ということになりますが
ここまで医学は発展しているにもかかわらず風邪ウイルスを退治出来るような薬は未だに発見・開発されていません。
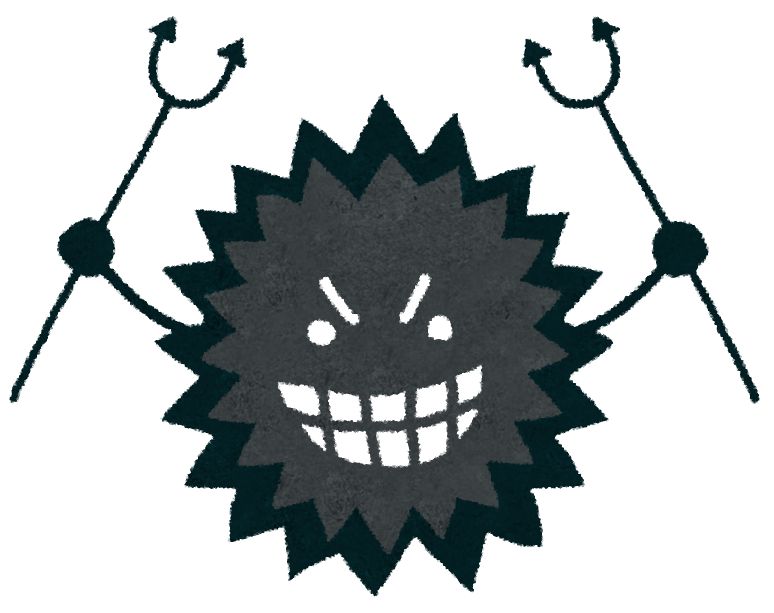
つまり
風邪に治療薬は存在しない!!
ということをまずは頭に入れておきましょう。
注:インフルエンザについては治療薬(ウイルスの増殖を抑える薬)が開発されています。
風邪薬の使い方
それでは風邪薬はなんのために使うのか?
それは生活(仕事)を楽にするためです。

- ・熱が高くて仕事にならない
- ・頭痛が酷くて家事が出来ない
- ・鼻水、くしゃみが酷く作業がはかどらない
- ・咳が激しく、周りに迷惑をかけてしまう
など、不快な症状を緩和させることで、生活しやすくするために使います。
風邪薬を飲んだからといって、風邪が治る訳ではありません。
風邪によって出てきている症状を薬の力で抑えるだけです。
総合感冒薬と呼ばれるような風邪薬には、解熱鎮痛剤・鼻炎薬・咳止めなどの薬がセットで配合されています。まるっと風邪の症状に対応出来るようになっています。
一方、医学的な知識が一定以上ある方では、出ている症状に対応出来るように薬を飲み分けている方もいらっしゃいます。
- ・熱が高いから解熱剤
- ・頭が痛いから鎮痛剤
- ・喉が痛いから鎮痛剤
- ・鼻水が酷いから鼻炎薬
- ・咳が苦しいから咳止め
などです。

痛み止め
総合感冒薬では、必要のない薬までセットで服用してしまうので、要らない成分は服用したくないという方は症状に合わせた薬を服用されると良いです。
風邪薬の大きなデメリット
この記事を書いた一番の目的は、風邪薬のデメリットをお伝えしておきたいためです。
風邪薬は治療薬ではないとしたのは上述の通りです。
さらに言えば、風邪薬は風邪が治るのを遅らせるものでもあります。

このあたりは製薬会社さんにとても怒られそうです。
それでは解説していきます。
風邪の際に出てくる症状にはしっかりとした意味があります。
・発熱
体温を上げることで免疫力を上昇させています。
1℃体温が上がることで免疫力は10倍になると言われています。
・くしゃみ、鼻水
体に入ってきたウイルスを排泄するために行われています。
・咳
同上です。ウイルスを排泄するためのものです。
・頭痛、喉の痛み
これらの症状については、付随症状ですので特に意味はありません。
感染に伴う炎症・充血反応から結果的に出てきてしまう症状です。
なのでこれらの症状については、今回は除外して考えていきます。
(強いて言えば、痛みを出すことで静養を促すためでしょうか。)
さて、ここで風邪薬を飲むことにしましょう。
発熱
→熱が出たので熱を冷ましたいと解熱剤を服用しました。
→熱が治まり、スッキリとしました。
→しかし、熱が上がったのは免疫力を上げるためでもありました。
→熱が下がったことで免疫力も低下し、結果的に風邪が長引く結果に。
鼻水・くしゃみ・咳
→これらを止めたいので鼻炎薬や咳止めを服用しました。
→症状が軽くなりスッキリです。
→しかし、ウイルスを排泄する行為を止めてしまいました。
→ウイルスは体に残りやすくなり、結果的に風邪が長引く結果に。
つまり、服用すると症状は緩和され楽になるが、風邪の治りはかえって遅くなる。
それが風邪薬です。
(だいぶ極論です。もちろん例外もあります。)

まずはこれを頭に入れておきましょう。
風邪の時に出てくる症状は意味のあるものです。身体が風邪ウイルスと戦っているために出ています。邪魔をせずにご自身の免疫力に任せましょう。
風邪薬の正しい使い方
それでは風邪薬はどのような時に使うべきなのでしょうか。
それは「治りが多少遅くなっても良いから、今の生活・仕事を乗り切らなくてはならない時」です。
治りが遅くなることは受け入れた上で、それでもなお服用をしなければならないと感じた時に服用しましょう。
・大事な仕事(用事)でどうしても休む訳にはいかない。
・今家事を済ませないと後々より大変なことになる。
・目を離せない小さな子供が居る。
など、しっかりとした理由があること。
また、これとは別で体温が39℃を超えたあたりからは、高熱によって体力を奪われていく状況にもなるため、高熱になり過ぎた場合には熱を抑える方が良い場合はあります。
(熱が高くても全く平気な方もいるので、このあたりは人によるかと思います。)
風邪を治すためにと思って、風邪薬を服用するのは間違いです。
風邪薬は症状を緩和するためだけのものであり、デメリットもあると理解しておきましょう。

この点を意外と理解していない方が多いので、お伝えがてらひとりごととして呟いてみました。
風邪の時はどうすれば良いの!?
そこで結論です。
最短で風邪を治したい場合は、家で布団で安静にしておくこと

です。
余計なエネルギーは使わないこと。
体内の全てのエネルギーを回復力に回せるように、出来るだけ安静にしておきましょう。
風邪の時には栄養のあるものをという考え方は戦前のものです。
現代では体内に既に風邪と戦うためのエネルギー(栄養)は十分に蓄えられています。
わざわざ栄養のあるものを食べる必要はありません。
実際、消化・吸収を行うことにもエネルギーが消費されてしまうため、不要に食事を摂り過ぎると消化・吸収のためにエネルギーロスが起こります。
無駄な飲食は行わず、それこそおかゆなどの消化に優しい食事を心掛けましょう。

何か摂っておいても良いものがあるとすれば、風邪の時に消費されやすいビタミンやミネラルなどで十分かと思います。
サプリメントや栄養ドリンク、スポーツドリンクなどで多少補給してみて下さい。
あとは 寝ておくこと です。
もちろん個々で生活や仕事の事情は違いますので、安静に出来る状況にあるのであればです。
無暗に風邪薬を服用して、意図せず回復を遅らせることのないようにはしておきましょう。
漢方薬の風邪薬は??
漢方薬の風邪薬については、また長くなりそうなので別に呟いていきたいと思います。
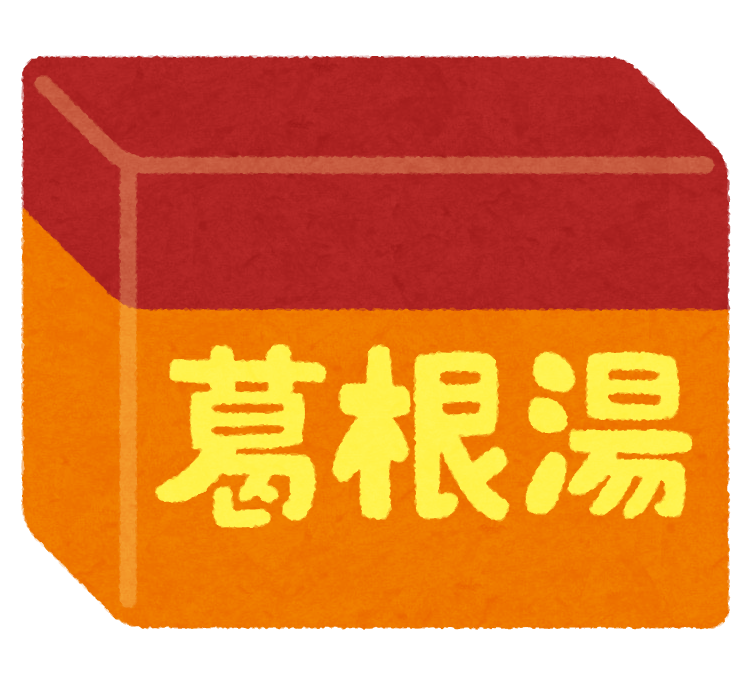
正直なところ、漢方の風邪薬は使いにくく、あまりお勧めはしていません。
漢方薬の使い方を正しく理解することが難しいためです。
これも漢方薬メーカーの方に怒られそうです。すみません。
ただし、身近に漢方薬局があり、風邪の時に毎回相談に行けるような時には、相談して利用するのは良いと思います。自己判断が難しいのです。
番外編
細かいところですが、薬の効能・効果の部分に関係する部分についてもお話しておきます。
解熱鎮痛剤と呼ばれるものについてです。

字のごとく解熱作用と鎮痛作用のあるものを解熱鎮痛剤と呼びますが
この解熱作用と鎮痛作用はセットになっています。
熱を冷まそうと解熱剤を服用するともれなく鎮痛作用もセットになります。
もう一方で痛みを抑えようと鎮痛剤を服用するともれなく解熱作用もセットになってついてきます。
どちらか片方の作用だけを都合よく享受することは出来なくなっています。

難しい
つまり、風邪を引きました免疫力は下げたくないので「解熱剤は服用したくない」のだが
頭痛と喉の痛みがあるから「鎮痛剤は服用したい」という希望を叶える事が出来ません。
頭痛や喉の痛みを抑えることは風邪の回復に大きく影響を与えることはないと考えられますが
鎮痛剤を服用すること=熱を下げること
に繋がってしまいます。
このあたりはもどかしいところですが、トレードオフの関係(どちらかしか得られない)となります。
頭痛や喉の痛みは作業効率を落としやすいので、仕事をする上では抑えておきたいものになります。
(発熱だけなら問題なく動けるという方は多いかと思います。)

- ・風邪を最短で回復させるには、薬は服用せずに安静にしておく。
- ・仕事が出来るくらいの体調であれば、薬は服用せずに働く。(他者への感染にはもちろん注意。)
- ・仕事に差し障りのある程度の症状が出ている場合は、仕方がないので最小限の薬の服用で済ませておく。
- ・仕事が出来ないほどの不調があれば、自宅で安静にしておく。
というあたりが、選択肢になるかと思っています。
痛みだけ抑えてくれる薬が開発されるだけでも、だいぶ楽になるとは思うのですが。
今後に期待しています。
ちなみに頭痛はなく、喉の痛みだけということであれば解熱作用の無い薬もあるのですが
肝心の喉の痛みを抑える作用があまり強くありません。服用しておけば少し楽になるかなという程度です。
こちらも今後の医薬品開発に期待したいです。
最後に
悪い癖で長い文になってしまいました。申し訳ありません。
風邪薬の適切な使用法、注意点(デメリット)とご理解いただけましたでしょうか?
細かい部分について言えば、ツッコミどころのある内容かと思いますが
当店としては大きな意味合いとして、風邪薬に対してこうした考えを持っています。
参考にしてみて下さい。
また、いずれ漢方薬の風邪薬についても記事化していきたいと考えています。
気長にお待ちください。
最後までお読みいただきありがとうございました。